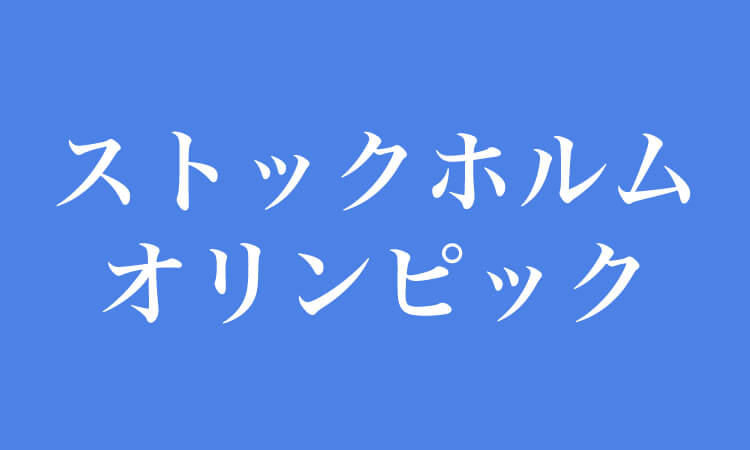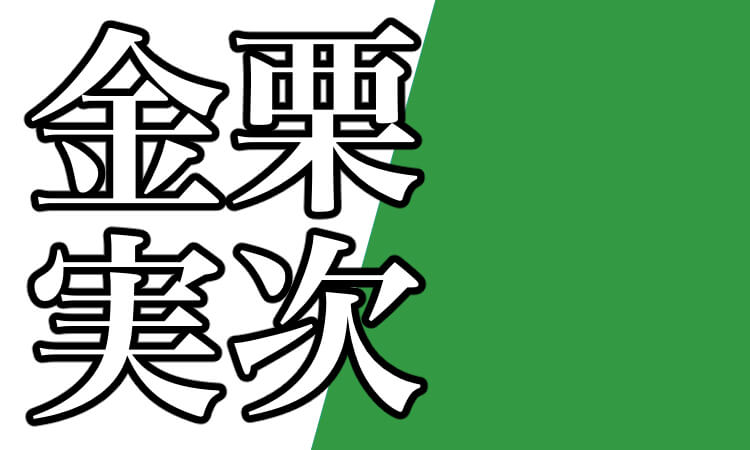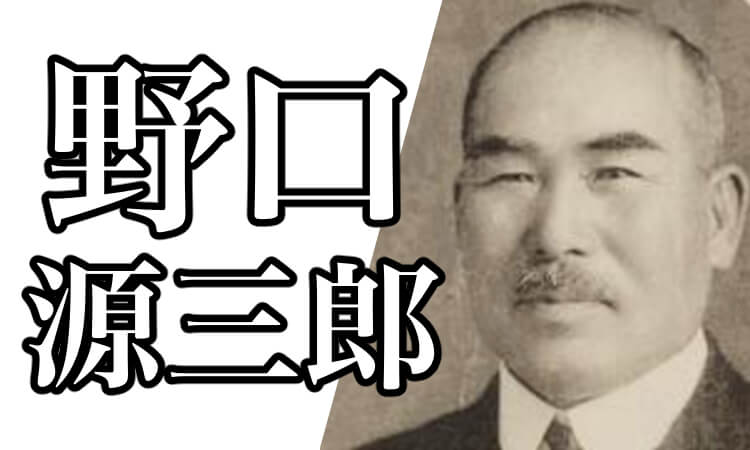毎年、正月2日、3日にお屠蘇気分でテレビの前に座っている人々を感動の渦に巻き込むスポーツ大会。
その大会の名前は通称「箱根駅伝」、正式名称を「東京箱根間往復大学駅伝競走」と言います。
東京大手町読売新聞本社前をスタートして箱根町芦ノ湖駐車場入り口の往路5区間と、これを逆に走る復路5区間の合計10区間を襷を繋いで走る駅伝は毎年多くの感動を与え、テレビ中継も高視聴率をマークしています。
今回取り上げる主人公はこの「箱根駅伝」の創設に尽力し、日本マラソンの父と呼ばれた人物、金栗四三(かなくりしそう)です。
2019年のNHK大河ドラマの主役に選ばれ、足袋をはいてマラソンを走り、大阪名物であるグリコのネオンサインのモデルとなった人物は、どのような人生を送ったのでしょうか?
日本マラソンの父・金栗四三の生い立ち
日本陸上の歴史では著名な人物である金栗四三も、学校で習う教科書では名前を見ることができないどころか、その認知度はほぼ皆無なので彼の生い立ちから丁寧に足跡を辿ってみようと思います。
1891年(明治24年)8月20日、熊本県玉名郡春富村(現在の玉名郡和水町)で父・信彦、母・シエの間に8人兄弟の7番目の子供として誕生しました。
子供の頃から勉強は良く出来たそうで、吉地尋常小学校、玉名北高等小学校、玉名中学校へと順調に進学、成績も学年で1、2位だったそうです。
また小学校へは片道12㎞の道のりを早足、または走って登下校し、中学校は寮へ寄宿しましたが、週末には片道20㎞を走って実家へ戻っていました。
成績優秀であったため、上級校への進学を進められた金栗四三は海軍兵学校を受験しますが角膜炎のため不合格となり、滑り止めで受験した東京高等師範学校(現在の筑波大学)に合格し、ここへ進学することとなりました。
生涯の師・嘉納治五郎との出会い
明治43年(1910年)4月、東京高等師範学校・地理歴史科に入学した金栗四三は、ここで自分の人生を決定付ける人物と出会います。
その名は嘉納治五郎。
柔道の父であり、講道館を設立して柔道の普及に尽力し、また日本の教育界にも多くの功績を残した人物です。
金栗四三が入学したとき嘉納治五郎は東京高等師範学校の学校長をしており、「知育、徳育、体育の三育」を教育理念に掲げ、勉学だけでなくスポーツを推奨して学校でも年に2回、マラソン大会を開催していました。
入学直後の春の大会に出場した金栗四三は、はじめての競技会ということもあり、アクシデントが重なり何とか25位でゴールという結果に終わります。
雪辱を期した秋の大会では1、2位は上級生に譲ったものの3位でゴールし、嘉納治五郎校長から「1年生としては抜群の健闘」と激賞され、2年生進級とともに熱心に入部を勧誘してくれた徒歩部(陸上部)に迷うことなく入部しました。
国内無敵の金栗四三、オリンピックへ
当時の学校のクラブ活動は学業の延長だったため、厳しい練習を課せられることはなかったのですが、金栗四三は自分に厳しい練習ノルマを課して努力を重ね、校内のみならず学生界でも敵なしのマラソンランナーへと成長します。
このころ校長であった嘉納治五郎は東洋ではじめてのIOC委員(国際オリンピック委員会)に選出され、1912年の第5回ストックホルムオリンピック(スウェーデン)への日本の参加を求められていました。
嘉納治五郎はオリンピックへ参加すべく関係機関に働きかけますが、政府の腰は重く文部省はこれを断り、仕方なく東京都内の大学有志を招集して大日本体育協会(のちのJOC、日本オリンピック委員会)を設立、初代会長に就任し出場選手を決めるべくオリンピック予選会の開催へと漕ぎ着けます。
この予選会に出場した金栗四三は日本には存在しなかったランニングシューズの代わりに足袋を履き出場、途中で足袋が破れて素足になるアクシデントがありながら、当時のマラソン世界記録を27分も上回る記録で優勝して世界を驚かせました。
日本人初のオリンピック選手
予選会に優勝した金栗四三と東京帝国大学の短距離ランナー・三島弥彦(みしまやひこ)をストックホルムへ派遣するとJOCでは決定するのですが、金栗も三島も当初は固辞したり、躊躇します。
その理由は当初は補助を約束していた文部省が「官立大学の学生が運動競技と言う遊びで海外へ行くなど許しがたい」として補助金の交付を拒否し、渡航費用が全て個人負担となったからです。
また、ストックホルムへ行ってオリンピックに参加するとなると5ヶ月もの長期に渡って学校を休まなければならず、進級や卒業、試験のことなど問題が山積していました。
代表を固辞する金栗四三に嘉納治五郎が「捨て石や礎になることは辛いことだが、誰かがやらなければいつまでも日本は欧米に追い付くことはできない。ここを逃せば次はまた4年も待たなければならない。日本のスポーツ界のために黎明の鐘になってくれ」と説得。
この「黎明(れいめい)の鐘」、物事の始まり・夜明けを告げる鐘という言葉に感銘を受けた金栗四三は出場を決意します。
世界への挑戦に多くの支援
オリンピックマラソン代表を受諾した金栗四三は父の亡きあと、全ての面で支えてくれている兄・金栗実次(かなくりさねつぐ)に渡航費用1800円の用立てを依頼する手紙を書きました。
実次は四三が代表になったことを非常に喜び、渡航費用は田畑を売っても用意すると約束してくれます。
ところが、この話を聞き付けた郷土の先輩で東京高等師範学校寄宿舎の舎監(寄宿舎住人の指導、管理をする人)であった福田源蔵(ふくだげんぞう)は金栗四三後援会を立ち上げ、渡航費用の寄付活動を開始、自身も必勝祈願として11円11銭を寄付すると、瞬く間に1500円もの金額が集まりました。
当時のストックホルムへの渡航費用は1800円程度(約500万円)だったため、兄・実次は残りの300円のみの負担ですみました。
予選途中で破れた足袋の対策を近所の足袋店「播磨屋足袋店」の職人・黒坂辛作(くろさかしんさく)に相談したところ、足袋の底を3重に重ねて厚くする「マラソン足袋」の開発に成功します。
この話が池井戸潤著「陸王」のモデルとなっています。
苦労の連続、初参加のオリンピック
明治45年(大正元年・1912年)5月16日に日本を出発、17日間掛けて翌月2日にストックホルムへ到着、船でウラジオストック、シベリア鉄道を使っての疲労のたまる長旅でした。
ストックホルムの日本公使館が用意した宿舎は三階建ての部屋が狭く、食事も良いとは言えないホテルでしたが、それ以外にも北欧独特の白夜や回り全てが外国人(当たり前のことですが)の環境に神経をすり減らすことになります。
またコーチとして同行していた大森兵蔵(おおもりひょうぞう)が患っていた肺結核の具合が良くなく、金栗四三は一人での練習を余儀なくされ、タイムを計ることさえ儘ならない状況となります。
しかし、金栗四三らが到着してから5日後、嘉納治五郎ら日本代表役員が到着し、多少なりとも事態は好転します。
オリンピックの開会式を4日後に控えた7月2日、オリンピック大会事務局から初参加である日本代表のプラカード表記についての問い合わせが来ます。
コースの大森は当然「JAPAN」とすべきだと提案しますが、金栗四三はイギリスが勝手につけた名前は嫌だと拒否し漢字で「日本」とすべきと主張。
困った嘉納治五郎がローマ字による「NIPPON」を提案し、恩師の妥協案には反対しがたく、金栗四三もこれを受け入れます。
ストックホルムオリンピック開幕
明治45年(1912年)7月6日、金栗四三は「NIPPON」表記のプラカードを持ち、三島弥彦が日章旗を掲げて入場、日本がはじめてオリンピックに名を刻んだ瞬間でした。
三島弥彦は100m、200m走の予選に出場しますが、自己新記録をマークしても最下位となり、世界との差を痛感させられます。
金栗四三はマラソンに出場予定でしたがスタート地点までの送迎車が来ず、スタート直前に到着するアクシデントに見舞われます。
参加選手68名ながら、アジア地区からの出場は金栗四三だけでした。
スタートして金栗四三はいきなりの試練にも直面します。
外国人選手との対戦経験がなかったため、彼らがスタートからいきなり全力でハイペースで飛ばすのに巻き込まれてオーバーペースとなり、自分のレースが出来ませんでした。
しかし健闘を続けた金栗四三は17位まで順位を上げ、折り返し地点を通過。
舗装された硬い路面、白夜による寝不足、気温35度を越える猛暑に満身創痍でフラフラとなった金栗四三は26.7㎞地点でコースを外れてしまい森の中で昏倒、そのまま意識を失います。
オリンピック閉幕、ここから得たものとは
意識不明の金栗四三はスウェーデン人の農夫エルジエン・ペトレに発見、救護され、命に別状なく介抱されました。
ストックホルム大会のマラソンは34名が棄権、一人が死亡する過酷なサバイバルレースとなりました。
金栗四三は大会本部に棄権届けを提出し忘れたため、記録は「棄権」ではなく「行方不明」扱いとなり、この事がのちに大きな感動を呼ぶことになります。
帰国の途についた金栗四三は、思ったような結果が残せず、非常に落胆していました。
しかし、嘉納治五郎だけは「オリンピックに参加したことによって外国の技術の高さや国際大会を経験できたことで日本のスポーツ界が世界への第一歩を踏み出せたことが有意義だった」と参加した者を励まし、次への飛躍を誓うのでした。
明治45年(1912年)9月18日、神戸港へと帰国した金栗四三らでしたが7月30日に明治天皇が崩御した事で日本中が悲しみのなかでの帰国となったため、出迎えるものもほとんどなくオリンピック参加も話題になることはありませんでした。
ベルリンへ向けてプライベートも充実
東京高等師範学校へ戻った金栗四三は勉学と4年後のベルリン大会を目指して練習を開始、この頃から後輩への指導も始めました。
金栗四三が23歳になった時、熊本県玉名郡小田村の資産家・池部氏から兄・実次を通して金栗四三に養子の話が持ち込まれます。
特に断る理由のない金栗四三は東京に居住するのを条件に承諾、また兄の実次が勝手に決めてしまった同石貫村の医師の娘・春野スヤとの見合いを学校卒業後にすることになります。
師範学校の卒業が迫るなかで愛知一中への赴任が決まりますが、金栗四三はベルリンを目指すために師範学校の研究科への進学を希望、これが認められて東京に残ることになります。
師範学校を卒業すると熊本へ帰省、スヤと結婚し、池部の家に養子に入りますがこの後も通称では金栗四三を名乗りました。
奪われた夢、露と消えたベルリン
新妻・スヤを熊本に残して東京に戻った金栗四三はストックホルムの反省を糧にベルリンを目指します。
夏の大会の猛暑に慣れるための訓練や米のない海外でパンでの食事、硬い路面の舗装道路対策など、経験したことすべてを練習に取り入れます。
また師範学校の先輩たちが赴任する各地の学校へ出向いて指導を行い、マラソンの普及に勤めました。
これらの費用は養母・池部幾江が仕送りしてくれたお金が充てられていたそうです。
ベルリンに向けて準備を進めるなか、大正3年(1914年)ヨーロッパではオーストリア皇太子暗殺に端を発した第一次世界大戦が勃発、世界を巻き込んだ戦争は大正5年になってもおさまらず、ベルリンオリンピックは中止が決定、金栗四三は26歳と言う年齢的にも能力的にも脂の乗った競技適齢期を戦争によって奪われてしまいます。
しかし金栗四三はこんなことには挫けることなく、次のアントワープへと気持ちを切り替えます。
マラソンの普及と箱根駅伝の胎動
東京高等師範学校研究科を卒業後、神奈川師範学校に赴任、兵役はオリンピックでの活躍こそが日本国のためと判断されて免除となったため、金栗四三はより一層マラソンや長距離走の普及、強化に力を注ぎます。
大正6年(1917年)読売新聞の記者の発想から考案された「東京奠都記念東海道五十三次駅伝徒歩競走」や、高地トレーニングになるとして富士登山マラソンの復活、朝日新聞との提携で実現した下関~東京1200㎞走破、大正8年(1919年)には日光~東京130㎞マラソンを開催し、マラソン選手の発掘、育成を強化していきます。
大正8年10月、金栗四三とマラソン選手の沢田英 一(さわだえいいち)と棒高跳び選手の野口源三郎(のぐちげんざぶろう)の3人が集まった時にサンフランシスコ~ニューヨーク間、アメリカ横断駅伝の構想が話題に上ります。この話を報知新聞社に持ち込むと協賛を取り付けることができ、国内でアメリカ横断駅伝の予選会を行うこととなります。
これが箱根駅伝の前身となります。
箱根駅伝の誕生とアントワープ五輪
アメリカ横断駅伝の予選会には東京高等師範、早稲田、慶応、明治の4校が名乗りをあげ、第1回箱根駅伝は四大校駅伝競走の名で開催されることになります。
日光、水戸、箱根の各地と東京を結ぶコースが候補となるなかで険しい山越えがある箱根が選ばれ、時期も耐寒のため2月となりました。
大正9年2月14日午後1時にスタートした第1回大会は東京高等師範学校が優勝、ここから箱根駅伝の伝統が築かれていきます。
この年の4月、金栗四三は30歳を迎えていましたがオリンピック予選を通過して代表に選出され、アントワープ五輪に派遣される選手は金栗四三を含めて15名、長距離走への出場選手は6名を数えました。
わずか二人で参加したストックホルム五輪の経験を活かして派遣選手の体調管理、宿舎の確保など、格段の進歩を見せてテニスで2つの銀メダルを獲得します。
金栗四三はマラソンで最高5位まで順位を上げますが、途中で足を痛め最終結果は16位でした。
女子スポーツの拡充とパリ五輪
オリンピックから帰国すると、金栗四三は東京女子師範学校(現在のお茶の水女子大学)に就職し、女性のスポーツ進出に力を入れます。
海外では女子選手の活躍も当たり前のようになっていましたが、日本では大和撫子、内助の功と言われる時代。
そんな日本の女性にもスポーツに参画してもらい、子供たちも幼少期からスポーツに触れ合える社会構造を目指しました。
この努力は大正12年(1923年)の関東女子体育連盟設立へと繋がっていきます。
パリ五輪開催の年に34歳となる金栗四三はマラソンの第一線を退こうと考えていましたが、出場した予選会で若手有望選手が次々と脱落、なんと金栗四三が優勝してしまいオリンピック代表に選出されます。
しかし出場した第8回パリ五輪では実力を発揮できずに32.3㎞付近で意識を失って脱落、棄権することになりました。
結局、3度の出場で一度も結果を残すことができずに金栗四三のオリンピック競技人生は幕を閉じました。
幻の東京オリンピックと恩師の死
昭和6年(1931年)、日本は東京へのオリンピック招致を表明、昭和11年の開催地決定投票でヘルシンキを破って招致が決定します。
東京開催の準備のためJOC初代会長、IOC委員の嘉納治五郎に東京へ呼び戻された金栗四三は選手の育成や会場構想などに奔走しますが、昭和12年の盧溝橋事件に端を発した日中戦争により、日本政府はオリンピック開催賛成派と反対派に別れて大いに揉めます。
嘉納治五郎はIOC総会で批判にさらされながらも東京開催の確認に成功しますが、この帰路に急性肺炎で急死。
結局、旗降り役の嘉納治五郎を失った賛成派は勢いを失い、政府は開催中止を決定し、ヘルシンキに開催権が移動。
東京オリンピックが幻となり、恩師・嘉納治五郎を失った悲しみは大きく、また戦争の影が社会からスポーツを奪い取ってしまい、金栗四三は失意のまま熊本に帰りました。
戦後復興と復活したマラソン
第二次世界対戦終結後、敗戦国の日本は14回のロンドン五輪は出場を拒否され、15回のヘルシンキからの復帰を目指します。
マラソン選手の育成のため、国際競走への出走を考えた金栗四三は「オリンピックマラソンで優勝する会」を結成して監督に就任、第55回ボストンマラソンに日本人選手をエントリーさせます。
この大会で広島出身の田中茂樹(たなかしげき)が「金栗足袋」を履いて優勝、ヘルシンキへの期待が高まりますが五輪本番では田中茂樹の25位が最先着と惨敗。
国民の期待を大きく裏切ったマラソンへの風当たりは強くなり、日本陸連はボストンマラソンへの参加に消極的になります。
金栗四三はこれに強く反対し、自らが監督となってボストンマラソンに参加、山田敬蔵(やまだけいぞう)が2時間18分51秒の驚異的な世界新記録で優勝、マラソンはヘルシンキでの汚名返上に成功しました。
東京オリンピック3位と金栗シューズ
この後もボストンマラソンで活躍を続けた日本マラソンですが、オリンピックでは成績を残すことができずにいました。
金栗四三はマラソン引退後も金栗足袋の進化、改良を続けており、ついに国産では初めてのランニングシューズてあるカナグリシューズの開発に成功、山田敬蔵のボストンマラソン優勝を支えたのも、このカナグリシューズでした。
日本のマラソンは昭和37年(1962年)に開催された東京オリンピックで円谷幸吉(つぶらやこうきち)が3位に入賞して銅メダルを獲得するまでオリンピックでの活躍はありませんでしたが、この後は1966年のメキシコ五輪で君原健二(きみはらけんじ)が銀メダル、1992年のバルセロナ五輪では森下広一(もりしたこういち)が銀メダルの成績を修めています。
54年ぶりストックホルムオリンピックでのゴール
昭和42年(1967年)、77歳になった金栗四三のもとに一通の招待状が届きます。
第5回ストックホルムオリンピックから55周年を記念して国際親善の式典を行うために記録を見直していたスウェーデンオリンピック委員会によって金栗四三の記録が抜け落ちている事が判明、また棄権届けも出ていなかったため、記録を完成させるためマラソンを完走してもらうように招待状を出したのでした。
これを快く受諾した金栗四三はスウェーデンに行き、マラソンで倒れたときに介抱してくれたペトレ氏の家を訪ね、子息に会ってお礼と思い出話に花を咲かせた後、ストックホルム記念球場に用意されたゴールテープを私服のまま切って55年ぶりに悲願のゴールを達成。
「日本の金栗選手、54年8ヵ月6日5時間32分20秒3の記録でゴールしました。」
このアナウンスが球場に響くと、客席から大きな拍手が沸き上がったそうです。
日本マラソンのフロンティア静かに眠る
昭和30年スポーツ界ではじめての紫綬褒章を受賞、他にもこれまでの功績を讃えた多くの賞を受賞し、玉名市の名誉市民にも選ばれました。
晩年は故郷の小学校でマラソンを教えていましたが、昭和58年(1983年)11月13日、恩師の嘉納治五郎と同じ肺炎でこの世を去りました。
享年93歳、死後、従五位銀杯が皇室から下賜されました。
はじめてのオリンピックに出場し、多くの苦難を乗り越え、日本マラソンを世界に通用するレベルに達成させるために数多くの功績を残した金栗四三。
彼の不屈の闘志とオリンピックに賭ける情熱が日本スポーツの大きな発展に繋がったのは間違いのない事実です。
2020年の東京オリンピック開催を誰よりも喜び、誰よりも楽しみにしているのは天国にいる金栗四三なのかもしれません。
足袋以外にも色々あった金栗四三にまつわる話
大阪の繁華街、一般にミナミと言われるエリアを流れる道頓堀川沿いに数多くの看板が掲げられています。
その中の一つ、戎橋の南西側に江崎グリコの陸上選手が両手を上げてゴールするデザインの看板があります。
1935年に設置されたこの看板のデザインはフィリピンのフォルチュナト・カタロン選手、陸上短距離のオリンピック選手・谷三三五(たにささご)とともに金栗四三を参考にしたものです。
また箱根駅伝で選出される最優秀選手に贈呈される賞を「金栗四三杯」と言います。
この金栗四三杯は富士登山駅伝にも創設されていて、一般参加の優勝チームに贈呈されます。
他にも金栗四三の名を冠にした大会も多く存在しており、故郷熊本にある熊本県民総合運動公園陸上競技場の愛称「KK ウィング」のKは九州、熊本と金栗のKを取ったものです。
(現在はネーミングライツの関係でえがお健康スタジアムになっています。)
日本独自のマラソンシューズ「マラソン足袋」
金栗四三はストックホルム五輪の予選会では既存の足袋を履いて出場しましたが、途中で底が耐えきれずボロボロに破れてしまい、裸足で走らざるを得なくなります。
そこで金栗四三は東京の播磨屋足袋店の職人・黒坂辛作とともに、底を3重に張り直したマラソン足袋を開発します。
これを履いてストックホルム五輪に出場しますが、底は持ちこたえたものの舗装された道路の固さに膝が耐えきれず、クッション性の高さが求められることを痛感します。
帰国後、黒坂とともにマラソン足袋の改良に着手し、足袋の留め具を外してスニーカーのように足の甲を紐で結ぶタイプとし、底にはゴムを張り付けてクッション性を持たせました。
大正8年、この足袋を播磨屋足袋店が「金栗足袋」として発売を開始し、金栗は一線退いていましたがアムステルダム五輪では金栗足袋を履いた日本人選手が4、6位に入賞、次のベルリン五輪では当時日本の占領下であった朝鮮半島出身の孫基禎(そんきてい)が優勝を飾りました。
金栗四三にとって、選手として満足のいく成績は残せなかったオリンピックでしたが、足袋の開発者としては見事に金メダルに獲得したのでした。
2019年NHK大河ドラマ「いだてん」
2020年の東京オリンピック開催を盛り上げるために、2019年のNHK大河ドラマ「いだてん」は日本のオリンピック参加の歴史を振り返る脚本で製作されます。
脚本は「木更津キャッツアイ」「あまちゃん」の宮藤官九郎、日本が初参加した1912年のストックホルムオリンピックから1964年の東京オリンピックまでを壮大なスケールで描く予定になっています。
当然のごとく主役は今回取り上げた金栗四三、そして彼を支えた多くの人々が登場する予定なので、どのようなキャスティングになっているのか簡単に触れておきます。
金栗四三・中村勘九郎(なかむらかんくろう・6代目)
近年は歌舞伎以外での活躍も目覚ましく、2016年「真田十勇士」、2017年「銀魂」と大ヒット映画に出演、大河ドラマは2004年「新選組!」の藤堂平助役以来となります。
嘉納治五郎・役所広司(やくしょこうじ)
押しも押されぬ日本を代表する俳優で「Shall we ダンス?」「関ヶ原」など数多くの映画ドラマに出演しています。
大河ドラマは「獅子の時代」「おんな太閤記」「徳川家康」「いのち」「花の乱」に続いて6作目になります。
金栗実次・中村獅童(なかむらしどう)
歌舞伎役者、俳優で活躍する傍ら、京都文教大学の客員教授を勤めるなど多彩な才能を発揮しています。
大河ドラマは今回が「春日局」「毛利元就」「武蔵MUSASHI 」「新選組!」「八重の桜」に続いて6作目となります。
他の出演者
他にも、三島弥彦・生田斗真、春野スヤ・綾瀬はるか、大森兵蔵・竹野内豊、黒坂辛作・ピエール瀧などが予定されていて、どのようなストーリーで観る人を魅了してくれるのか、期待を持たせるキャスティングです。