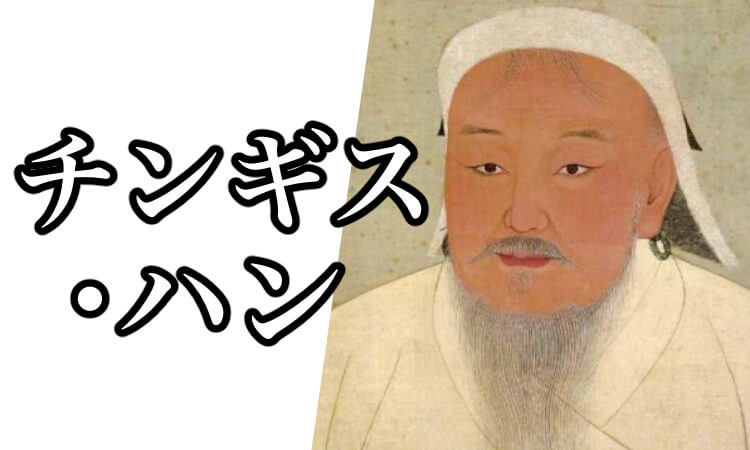フビライハンとは、チンギスハンの孫でモンゴル帝国第5代帝王となった人物です。
東南アジアまで勢力を広げたモンゴル帝国は鎌倉時代中期に日本に2度にわたって侵攻(元寇)を行うも失敗に終わりました。
そんなフビライハンの生涯や元寇、また源義経と子孫について解説していきます。
フビライハンの生い立ち
フビライハンは1215年、チンギスハンの四男・トルイと母であるソルコクタニ・ベキの次男として誕生しました。
よってフビライハンはチンギスハンの孫にあたります。
兄は後に第4代皇帝となったモンケであり、弟はイルハン朝を開いたフレグ、また後にフビライハンと皇帝争いを行うアリクブケがいたとされています。
1251年、兄・モンケが第4代皇帝になると、フビライハンはゴビ砂漠以南の南モンゴル高原・華北の諸軍の指揮権を与えられました。
1253年には雲南を支配していた大理国を降伏させます。
第4代皇帝である兄・モンケが病死
雲南からの帰還したフビライハンは、現在の内モンゴル自治区に位置する南モンゴル中部のドロン・ノールに幕営を中都(現在の北京)から移します。
この頃になると南宋および朝鮮半島の高麗征服の総指揮を取るようになっており、南宋征服に備え準備を行っていました。
しかし、兄・モンケは早急に南宋を併合することを望んでいたため、フビライハンを南宋作戦の責任者から更迭し、自ら陣頭指揮を取り始めます。
1258年に兄・モンケは自ら軍を率いて陝西に入り南宋領を転戦しましたが、翌年の1259年に軍中で流行していた疫病(赤痢)を患い亡くなりました。
第5代皇帝となる
第4代皇帝であった兄・モンケが亡くなったため後継者にフビライハンと弟・アリクブケが候補として名前があげられましたが、フビライハンはモンゴル貴族、王族を味方につけると1260年、フビライハンの本拠地、金蓮川においてモンゴル帝国における貴族や重臣たちが行う政治会議が開かれ、ここでフビライハンの皇帝即位が一方的に宣言されました。
これに対し、弟・アリクブケも皇帝即位を宣言し、これによってモンゴル帝国はフビライハンとアリクブケの2人の皇帝が誕生しました。
しかし1264年になると、弟・アリクブはフビライハンに降伏し、フビライハンは第5代皇帝となりました。
元の初代皇帝となる
1260年に即位したフビライハンはモンゴル帝国において初となる「中統」と呼ばれる中国風の元号をたてました。
また行政府である中書省、軍政を司る枢密院、監察を司る御史台などを設置し、中国式の政府機関を一通り整備します。
至元4年(1267)になると中国式の方形様式を取り入れた大都を(現在の北京の地に造営した都市)の建設を始めました。
その後、至元8年(1271)12月18日になると元号を「中統」から「元」と改め、元の初代皇帝となりました。
中国王朝化を目指す
フビライハンはモンゴル帝国の中国王朝化を目指していたため、中国王朝を真似た組織作りを行いました。
中国様式を様々な箇所で取り入れたモンゴル帝国でしたが、この頃はまだ遊牧の移動生活を保っていたとされ、遊牧国家であったとされています。
中国王朝化を目指すフビライハンに対し、弟・アリクブケはモンゴル高原を中心と考える守旧派でした。
軍事面や経済面
フビライハンは軍事面において妻・チャブイとの間に誕生したチンキム、マンガラ、ノムガンを燕王、安西王、北平王といった地域の軍隊を統括させます。
至元13年(1276)になると将軍・バヤンが南宋の都臨安を占領したため南宋は滅亡し、モンゴル帝国によってその大半の地域が支配下となりました。
この間、フビライハンはイスラム教徒を財務官僚として登用、商業税を充実、運河の整備などを行いモンゴル帝国の経済発展を行います。
経済が発展したモンゴル帝国にはヴェネツィア出身の商人マルコ・ポーロといった多くの人々が訪れました。
このように、イスラム教徒の登用やヴェネツィア出身の商人の来訪などもありフビライハンの治世は国際色豊かなものであったとされています。
また服属国である高麗で起こった三別抄の反乱の鎮圧、至元24年(1287)にはビルマのパガン王朝を事実上滅亡させるなど行いました。
元寇
東南アジアまでモンゴル帝国を広めたフビライハンは次に目を付けたのが日本でした。
フビライハンは日本に6度にわたってモンゴル帝国に服属するよう求めるも、日本からの返事が無かったため武力によって日本を侵攻します。
至元11年(1274)にモンゴル帝国は日本に侵攻してきますが失敗に終わり、再び至元18年(1281)に日本を襲撃しました。
日本において、この1度目の侵攻は文永の役、2度目の侵攻は弘安の役と呼び、2度のモンゴル軍の襲撃を元寇または蒙古襲来と呼びます。
2度にわたって日本の九州地方を襲撃したモンゴル軍でしたが、どちらも失敗に終わりました。
各地で反乱が勃発
モンゴル帝国は勢力を伸ばし続けましたが、至元12年(1275)頃になるとモンケ家、アリクブケ家、コルゲン家などの王族たちが四男の北平王ノムガンが占領していたアルマリクで反乱を起こしました。
この反乱によって四男の北平王ノムガンの軍は崩壊し、この崩壊をきかっけにオゴデイ家のカイドゥが諸王家を統合しフビライハンに対抗してきます。
これに対し、フビライハンはバヤン率いる大軍をカイドゥのもとへ派遣したためカイドゥの反乱を防ぐことができました。
各地で反乱が勃発
至元10年(1273)には次男・キンチムが皇太子に冊立されます。
しかしアフマドは自身の党派に属する物を財務官僚に配置したため、アフマドの権力は絶大となりキンチムちアフマドは対立関係となりました。
ですが至元19年(1282)になるとアフマドはキンチムの党派に属する官僚に暗殺されたため政争はチンキム派が勝利となり、キンチムを阻む勢力はいなくなりました。
そのためフビライハンは次男・キンチムに譲位しようとしましたが、チンキムは至元14年(1286)に病死してしまいました。
反乱軍の指導者・ナヤンを破る
また至元15年(1287)には諸王家がオッチギン家の当主ナヤンを指導者として反乱を起こします。
この頃になると次男・キンチム、三男・マンガラはすでに亡くなっていたため、72歳であったフビライハンは自ら軍を率いて挙兵し、遼河でナヤンに勝利しました。
その後、ナヤンは処刑され、諸王家の当主たちも降伏したため鎮圧となります。
またオゴデイ家のカイドゥはこの混乱に乗じてモンゴル高原への進出を狙いましたがフビライハンによってカイドゥ軍は撤退に追い込まれました。
そしてカチウン家の王族カダアンはなおフビライハンに抵抗していましたが、至元29年(1292)皇孫テムルが派遣されカダアンは破られ戦死となりました。
反乱の鎮圧と財政難に追われた晩年
以前から財政難の危機に直面おり、財政再建のためウイグル人財務官僚・サンガに期待していたが失脚してしまったため、フビライハンの晩年は反乱の鎮圧と財政難に追われることとなりました。
至元30年(1293)になると次男・キンチムの息子・テムルを元軍の総司令官とし、フビライハンは翌年の至元31年(1294)2月18日、79歳で病死しました。
源義経との関わり
源義経は平安時代末期に活躍した武将で文治5年(1189)に亡くなった人物です。
フビライハンとは会ったこともなければ、活躍した国、時代も違います。
しかし、源義経には実はチンギスハンだったのでは。というチンギスハ説が存在します。
このチンギスハン説とは、衣川の戦いで亡くなったとされる源義経は実は生存しており、蝦夷地に逃げた後、大陸に渡りチンギスハンになったのではないかという説です。
この説のようにチンギスハンが源義経であるのならば、チンギスハンの孫にあたるフビライハンは、源義経の子孫ということとなります。
ですがチンギスハンの両親の名前や出自などが判明しているため、源義経がチンギスハンであったということは考えられません。
フビライハンの子孫
フビライハンはコンギラト部族の出身のアルチ・ノヤン家の子女・チャブイを至元18年(1281)まで妃とすると、至元14年(1286)から至元13年(1294)までの間、同じくコンギラト部族首長家アルチ・ノヤン家の子女・ナムブイを妃としました。
その他にも複数の妃がいたとされています。
フビライハンの子供の数は『集史』には12人、『元史』には10人と記載されています。
フビライハンの祖父、チンギスハンはフビライハンを含め多くの子孫を残しました。
それらの子孫たちはロシア貴族やヨーロッパ貴族とも婚姻を結んだとされ現在でもチンギスハンの子孫たちはヨーロッパに多く存在しているとされています。
2004年に英レスター大学で行われた研究では、チンギスハンの男系子孫は世界で約1600万人もいるという事が判明しました。
まとめ
フビライハンは初代モンゴル帝国の皇帝チンギスハンの孫で5代目モンゴル帝国皇帝となった人物でした。
また中国風の元号「元」を用い元の初代皇帝となりました。
至元11年(1274)と至元18年(1281年)に日本の九州地方に侵攻してきた元寇では、日本を破ることができませんでしたが、至元28年(1291)には3度目となる日本の侵攻を計画していたとされています。
しかし、財政難に追われていたためその計画は破棄となり、これによって日本は3度目の蒙古襲来の危機を脱したのでした。