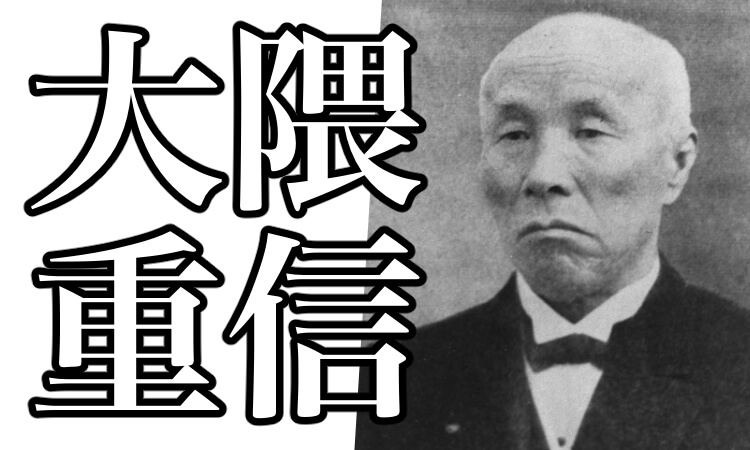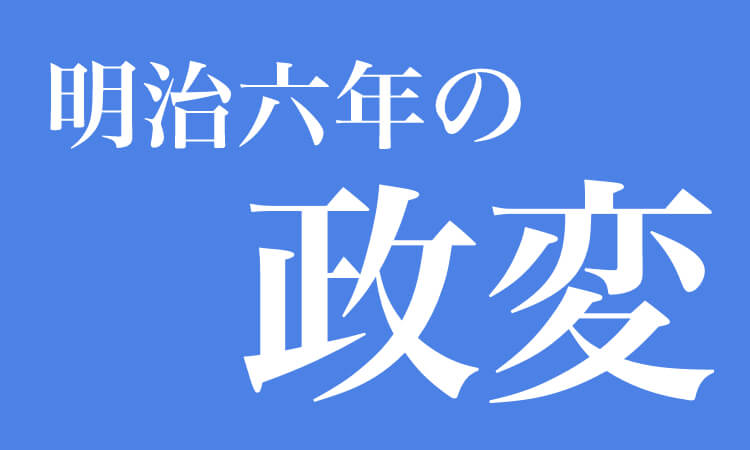明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年9月13日)まで欧米諸国の視察に出た岩倉使節団の留守を預かった西郷隆盛を首班とする政府が、武力をもって朝鮮を開国させることを目的とした主張を征韓論といいます。
当時の朝鮮は鎖国政策を取っており、軍隊を送る事で開国させようという考え方が日本で主流となりました。しかし欧米視察から戻った岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らはこの征韓論に猛反対しその結果、朝鮮派兵は中止されます。
これを不服とした西郷隆盛らは職を辞して下野し、最終的には明治新政府を二分する西南戦争を引き起こしてしまいました。
これだけの対立をもたらした征韓論とはいつどこで生まれて、何を日本にもたらしたのでしょうか?征韓論における西郷隆盛の関わりなどを含め、わかりやすく解説していきます。
征韓論が起こった背景
日本と朝鮮には室町時代から朝鮮通信使の往来があり、国交も対馬藩を通して継続して維持されていました。
しかし、八戸順叔による新聞への征韓論寄稿による日朝関係の悪化(八戸事件)や朝鮮国王の父である大院王(だいいんおう)による鎖国政策と丙寅洋擾(へいいんようじょう)によるフランス帝国への勝利、ジェネラル・シャーマン号事件での米国帆船撃退など欧米列強に対する勝利で対外強硬路線をとる朝鮮と日本が対立するなかで、日本では明治新政府が誕生しました。
日本はこれまでの慣例通り新政府の発足と国交の継続交渉を行おうとしますが、朝鮮側に文書不備を理由に拒否されます。
日本側は繰り返し交渉使節を送りますが朝鮮側は全くこれに応じず、排日の空気が強くなり政府主導のボイコットまで起こります。
ここまで来ると日本国内でも征韓論が強く主張されるようになり、閣議でも朝鮮派兵が議論されるようになりました。
征韓論とは?
では、この征韓論とはどこから出てきた考え方なのでしょうか?
もともと日本書紀では高句麗・新羅・百済を「三韓」と呼んでおり、朝鮮とは李氏朝鮮が正式国号として使用していたものだったため、日本では「韓」と呼称するのが通常でした。
江戸後期に儒学に対抗して賀茂真淵(かものまぶち)、本居宣長(もとおりのりなが)が確立した古道説が平田篤胤(ひらたあつたね)によって復古神道として提唱され、これが幕末の尊王思想へと繋がります。
また儒学に国学や史学、神道を融合した学問が水戸藩で形成され水戸学として確立され、吉田松陰や西郷隆盛ら多くの幕末の志士に影響を与えました。
この水戸学や復古神道、吉田松陰が主宰する松下村塾(しょうかそんじゅく)では「古事記」「日本書紀」の中で古代日本が朝鮮半島の支配権を持っていたとする記述があることを教えており、これを根拠として朝鮮進出を正当化しており、勝海舟や橋本左内などの書き残した史料にもそれが垣間見えます。
これが尊王攘夷運動の政治的主張となり征韓論を産み出しました。
征韓論と西郷隆盛
1871年、岩倉使節団が欧米視察のために留守になるのを受けて、三条実美、西郷隆盛らに政務が一任されました。
その中に朝鮮政府の親書受け取り拒否の問題がありました。
交渉使節の派遣や朝鮮実情視察(密偵)を送った結果、国書の拒否、使節への侮辱、居留民の安全に対する脅威などが明かになり、朝鮮からの撤退か武力による朝鮮の開国かの二者択一を迫られることとなりました。
武力による修好条約締結を求める板垣退助(いたがきたいすけ)に対し、西郷隆盛は武力行使及び派兵には反対で、自身が全権大使として朝鮮へ行くことを主張しました。
数度にわたる議論の結果、西郷隆盛の全権派遣案は板垣退助、外務卿・副島種臣(そえじまたねおみ)の同意を得ること成功し、閣議決定され三条実美より明治天皇に報告がなされましたが、天皇より「岩倉具視の帰国を待つように」との勅旨があり、岩倉使節団の帰国を待つこととなりました。
征韓論に反対した岩倉具視、大久保利通の主張
1873年9月岩倉使節団が帰国すると、西郷、板垣、副島らの意に反して、岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らは朝鮮派兵どころか西郷隆盛の全権大使派遣にも反対の姿勢を打ち出しました。
これは岩倉使節団がイギリスやフランス、アメリカで見てきた産業革命による技術革新や植民地政策を日本でも早急に行い、欧米列強に追い付く必要を痛感し、蒸気機関の発達や紡績技術の進歩、それらによる軍事技術の進化など、日本も早期に富国強兵、殖産興業政策を着手する事に尽力すべきと考えたからです。
このため朝鮮派兵などの外事に貴重な国力を使うことを良しとせず、西郷隆盛らの征韓論、全権派遣に反対したのでした。
征韓論敗れる。明治六年の政変
岩倉具視や大久保利通ら帰国組が閣議に参加して、征韓論の是非が議論されましたがなかなか結論が出ず、一旦は西郷隆盛の派遣が閣議で決定されますが、大久保利通、木戸孝允、大隈重信(おおくましげのぶ)らが参議の、岩倉具視が右大臣の辞意を表明し、征韓論是非の対立は頂点に達しました。
太政大臣・三条実美はこの重圧に耐えられずに発病、太政大臣代行となった岩倉具視は全権派遣の閣議決定の上奏を拒否し、この間に宮中工作を行います。
西郷隆盛は最後の手段として自身の参議、陸軍大将、近衛都督の辞表を提出、岩倉具視らに圧力を掛けます。
岩倉は妥協案として閣議決定である全権派遣案と全権派遣延期案の二つを同時に上奏、明治天皇は延期案を採用したため西郷隆盛は辞職しました。
政府は参議及び近衛都督の辞職は認めましたが、陸軍大将の辞職は認めませんでした。
明治六年の政変で下野した人々
明治6年9月24日西郷隆盛が辞職、これを政府が認めたことが知れ渡ると、征韓論に賛成していた板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣は参議を辞職しました。
また、これに続いて征韓論、全権派遣賛成派であった林有造(はやしゆうぞう・高知県令)、桐野利秋(きりのとしあき・陸軍少将、陸軍裁判所所長)、篠原国幹(しのはらくにもと・陸軍少将、近衛長官)、淵辺群平(陸軍中佐)、別府晋介(陸軍少佐)・河野主一郎(近衛陸軍大尉)、辺見十郎太(近衛陸軍大尉)、村田新八(宮内大丞)・池上四郎(元陸軍少佐、外務省官僚)ら元薩摩藩士を中心に政治家、軍人、官僚らが続々と辞表を提出し、結果合計600名を越える人物が辞任して故郷へ帰りました。
征韓論のその後
征韓論を否定して、大使の派遣も却下した岩倉具視や大久保利通でありましたが、1874年には漂着した台湾で宮古島島民54人が虐殺される事件(宮古島島民遭難事件)が起こり、政府はこれに対して軍隊を台湾に送る台湾派兵を行い、征韓論に反対しながら台湾に兵を送るのは矛盾しているとして木戸孝允が参議を辞任しました。
1875年には朝鮮半島近海を航行中の日本艦船に朝鮮が砲撃をする江華島事件が起こり、結果的にはこれが翌1876年に締結された日朝修好条規へと繋がっていきます。
西南戦争の勃発など、内乱状態に
岩倉具視や大久保利通と対立して下野した人々は、当時の新政府の政策に不満を持っていた不平士族と結び付き、1874年に江藤新平、島義勇(しまよしたけ)らに率いられた佐賀の乱、前原一誠に率いられた萩の乱、そして極めつけは1877年に西郷隆盛率いる旧薩摩藩士を中核にした西南戦争が勃発し、日本は一時期内戦状態になります。
これら一連の不平士族の乱は政府軍の奮闘によって抑え込むことに成功しますが、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平(佐賀の乱で斬首)、副島種臣らが起こした自由民権運動はその後に紆余曲折を経て政党政治の誕生と帝国議会開設へと向かうことになりました。
征韓論まとめ
明治新政府を二分する大騒動となり、西南戦争という内戦まで引き起こした征韓論ですが、結論から言えば無意味な論争であったとも考えられます。
西郷隆盛らが下野してからわずかに3年で朝鮮との間には西郷留守政府が望んでいた日朝修好条規が締結され、朝鮮への出兵が現実化します。
これらの事から邪推すると西郷隆盛ら留守政府に手柄を取られたくなかった岩倉具視や大久保利通がわざと西郷隆盛らを追いやり、軍艦を江華島に派遣して朝鮮を挑発し砲撃させ、これを口実に武力的圧力を朝鮮に加えて不平等条約を結ばせたとも考えられます。
西郷隆盛が描いていた政治的日程通りに日朝修好条規が締結されながら、その1年後に西郷隆盛が挙兵したことには、この征韓論以外に大きな要因が明治新政府に対してあったのではないかと考えさせられてしまいます。
真実は新たな史料が発見されない限り闇の中ですが、岩倉具視や大久保利通の幕末期のいわく付きの所業を見るとありえない話ではないと思われるのです。