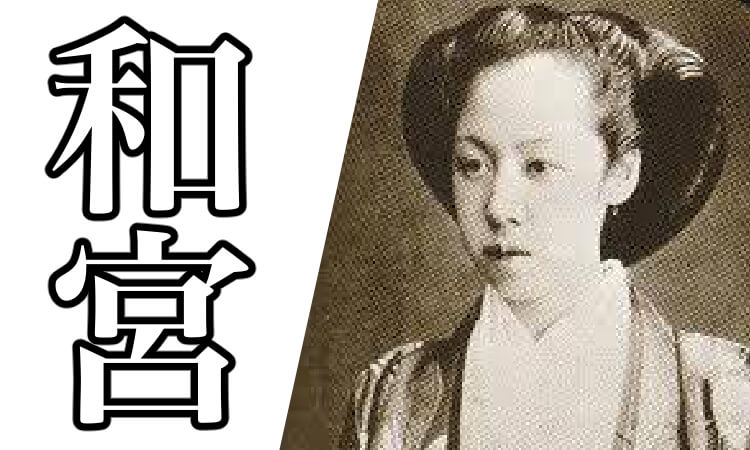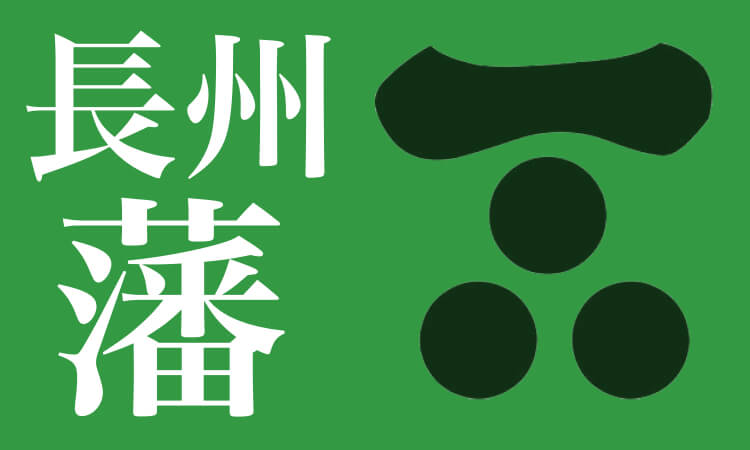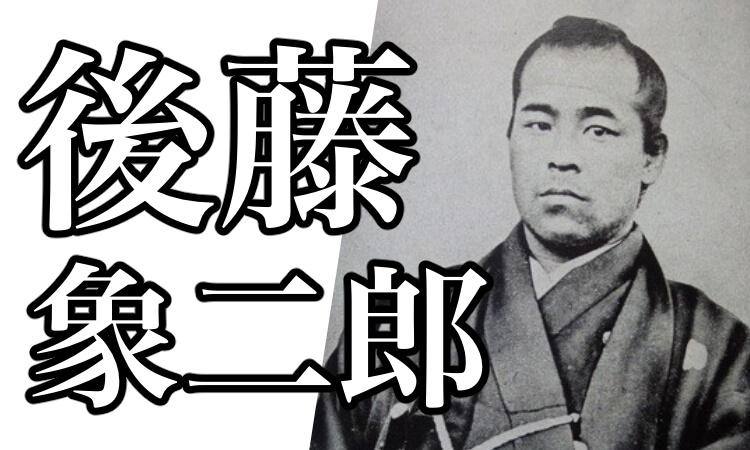中国紀元前770年から同403年の間、一般に春秋戦国時代と言われる時に誕生した言葉が1850~60年代に日本の若者たちを熱狂の渦に巻き込みます。
その言葉とは「尊王攘夷」(日本では天皇を敬うため尊皇とも書く)。
君主を尊び、外敵をしりぞけるという意味で、日本では天皇を尊び、外国(欧米列強)からの侵略を排除する考えで、幕末には学問として確立し藩校や私塾で教えられ、時代を動かす運動となり尊王攘夷派という大きな思想集団となっていきます。
この尊王攘夷という言葉が260年続いた徳川幕府を崩壊させ、明治という新しい時代を誕生させました。
今回はこの尊王攘夷という言葉や考え方がいつどこで生まれ、どのような事に影響を与えたのか、尊王攘夷運動の内容や攘夷派・反対派などについて解説していきたいと思います。
尊王攘夷、言葉の起源と意味
古代中国の春秋時代に周(しゅう)王朝の天子を尊び、夷狄(いてき・異民族のこと)を打ち払うという意味で、周王朝の君主であった斉国の桓公(かんこう)が周王を敬い、他の君主と一致団結して南方の異民族である楚を討伐したことを指しています。
これを日本の国学者が流用したのが日本国内での使用の始まりとされています。
鎌倉、室町時代は天皇を王とすることもよくあったのですが、江戸時代には天皇の呼称が確立し、幕末には「尊王」から「尊皇」へと変わっていきました。
幕末に「尊王攘夷」という言葉を最初に使ったのは水戸藩主・徳川斉昭が記した水戸藩藩校・弘道館記が最も最初であるとされています。
この弘道館記の起草者は藤田東湖(ふじたとうこ)であるため、幕末の尊王攘夷論は水戸学から大きな影響を受けています。
尊王攘夷運動が起こった背景
尊王思想というのはもともと鎌倉時代から存在しており、天皇を王、将軍(武家)を君主と考えて君主が衰えると王の権威を高めて利用するというのは過去の歴史でも建武の新政、安土桃山期など天皇の権威を利用しての治世は行われていました。
幕末期における徳川幕府も異国船の来航など外的圧力と幕府の失政による社会不安を天皇の権威を利用した尊王論によって乗りきろうと考えたのです。
この事によって必然的に天皇の権威が高まり、天皇中心の国家体制が考えられるようになります。
長く続く徳川幕藩体制に多くの綻びが見え始めた1853年、アメリカの東インド艦隊を率いてマシュー・ペリー提督が浦賀にやって来ます。
「泰平の眠りを覚ます上喜撰たつた四杯で夜も眠れず」と狂歌にも詠われた黒船来航です。
ペリーの目的は日本の開国、通商条約の交渉でしたが、幕府単独でこの問題を解決できないと判断した当時の老中・阿部正弘(あべまさひろ)がこの解決案を諸藩に諮問したため、外国の脅威から日本を守るために攘夷論が沸騰し、幕府の不甲斐なさから高まった尊王論と相まって尊王攘夷運動として一気に日本中に広まりました。
尊王攘夷運動に対する立場による思惑
1年後の返答を約束して一旦はペリーを追い返すことに成功するものの、翌年1584年の来日時には日米和親条約を締結、徳川幕府の鎖国政策に終止符が打たれます。
この4年後、日本総領事タウンゼント・ハリスと幕府の間で日米修好通商条約の交渉が始まりますが、幕府は度重なるハリスの恫喝に腰砕けとなり、朝廷に対して天皇の勅許を求めます。
しかし、岩倉具視(いわくらともみ)や中山忠能(なかやまただやす)ら少壮の攘夷派公家による抵抗運動(廷臣八十八卿列参事件・ていしんはちじゅうはちきょうれっさんじけん)や薪や食料の補給には「神国日本を汚すことにはならない」と賛意を示した孝明天皇も大きな変化をもたらす修好通商条約には難色を示し、勅許を拒否しました。
安政の大獄で攘夷派を処罰
アメリカと朝廷の板挟みとなった幕府は大老・井伊直弼の決断で無勅許による条約締結に踏み切り、これに反対する攘夷派を一掃すべく処罰を開始しました。
吉田松陰(よしだしょういん)、橋本左内(はしもとさない)の斬首をはじめ、14代将軍継嗣問題で徳川家茂のライバルだった一橋慶喜や御三家の藩主、公家、大名、幕臣、諸藩の藩士など身分の上下を問わず100名以上を処罰する大弾圧となりました(安政の大獄)。
尊王攘夷論に対する反対派・公武合体論
外敵を排除し天皇中心の国家体制を論じる尊王攘夷運動に対して、朝廷の権威と幕藩体制の改革強化によって体制を建て直そうとする公武合体論という攘夷反対派が現れます。
公武合体論は日米修好通商条約締結後、分裂状態となった朝廷、幕府、諸藩の関係を修復しようとする勢力から登場しました。
幕府の権威を朝廷の伝統的権威と重ね合わせて幕府権力を取り戻させ、朝廷と幕府の間の大政委任論(天皇が幕府に政権を委ねている考え)を明文化して、尊王攘夷派を押さえ込もうと言うものです。
この考えは越前藩の松平慶永(まつだいらよしなが)、薩摩藩の島津斉彬(しまづなりあきら)・久光(ひさみつ)、土佐藩の山内容堂(やまうちようどう)ら雄藩の藩主の多くが支持していました。
尊王攘夷派と公武合体派の主導権争い
安政の大獄のあと一時的に鳴りを潜めた尊王攘夷論でしたが、井伊直弼が桜田門外の変で暗殺されたため息を吹き返し、公武合体派とは一線を画す尊王攘夷派である長州藩は破約攘夷(条約破棄、戦争覚悟)を掲げて、京都に集まる急進尊王攘夷派の盟主となり、「天誅」なるテロ行為が横行する中で薩摩藩や土佐藩の急進派志士も加わり、孝明天皇天皇を擁して朝廷を自由に動かし、幕府に攘夷決行を迫りました。
公武合体派の巻き返し
公武合体派は老中・安藤信正(あんどうのぶまさ)によって公武合体政策である和宮降嫁(孝明天皇の妹である和宮を徳川家茂に嫁がせる)に成功しますが、尊王攘夷派からの反発にあって安藤信正は襲撃され、負傷し失脚(坂下門外の変)、島津久光や山内容堂らも京都を去り、京都は尊王攘夷一色に染まりました。
しかし劣性を挽回したい公武合体派による八月十八日の政変や禁門の変によって長州藩や、尊王攘夷派の志士たちは、京都から追い払われ政治改革の主導権は公武合体派が握ります。
欧米列強との間に起きた衝突
京都での立場を失っただけでなく、朝敵となった長州藩はこの時もう一つ大きな敵を抱えていました。
1863年、攘夷決行のため関門海峡(当時は馬関海峡)を封鎖、通過しようとする外国船を無差別に砲撃しました。
アメリカとフランスは対抗策として馬関海峡に停泊していた長州藩軍艦を砲撃し、これを壊滅しますが、長州藩は砲台を修復し海峡封鎖を続行します。
四国艦隊下関砲撃事件(下関戦争)の勃発
翌1864年、海峡封鎖による経済的損失に業を煮やしたイギリスはアメリカ、フランス、オランダに呼び掛け長州藩に対して報復措置を行うことを決め、実行に移します。(四国艦隊下関砲撃事件・下関戦争)
艦艇数17隻、総兵員五千名で馬関(現在の下関市)及び長州藩の砲台を徹底的に砲撃し壊滅させると陸戦隊を上陸させて馬関を占拠しました。
生麦事件で薩英戦争へ
同じ頃、薩摩でも似たような事件が起こります。
1862年、島津久光の行列に馬に乗ったイギリス人が乱入し、このイギリス人を薩摩藩士が死傷させる生麦事件が起こりました。
この生麦事件の解決と補償に関して対応を迫るイギリスとそれを拒否する薩摩藩との間で武力紛争がおこり、薩摩は城下の一割を焼失し集成館を始めとする軍事施設は壊滅し、艦船も多数失います。(薩英戦争)
イギリスにも大きな打撃を与えたとはいえ、薩摩藩が受けた被害は甚大でした。
攘夷実行は不可能と知り、開国へと向かう。
下関戦争に敗れた長州藩、薩英戦争で甚大な被害を受けた薩摩藩は欧米列強との技術力、軍事力の差を痛感します。
長州藩は諸外国と対立するよりも、その技術力や軍事力、軍制、戦術など学ぶためにイギリスに接近、また薩英戦争後に薩摩藩は攘夷の考えを捨てて開国し、外国の特にイギリスに接近して先進技術の導入と軍制の改革を行いました。
このように外国と直接戦闘を経験した雄藩である長州藩と薩摩藩は、攘夷活動がいかに無意味で無謀なものであるかを痛感し、日本を開国し産業を育成して欧米に追い付かない限り、日本に将来がないことを知ったのでした。
薩長同盟から大政奉還へ、そして倒幕完了
攘夷が不可能と悟った薩摩藩と長州藩は幕府中心の公武合体も時代についていけないことを知り、開国倒幕への道を選択します。
そのためには尊王の意識が高く、倒幕へ武力闘争も辞さず、海外の最新技術の導入に前向きな藩が手を組み、幕府を倒すことが日本を救う道と考え、まずは薩摩藩と長州藩の間に相互扶助同盟である薩長同盟が結ばれます。
大政奉還論の提唱
薩摩藩と長州藩が幕末政変の主導権を握るなかでこれに割って入りたいと考えた土佐藩参政・後藤象二郎は海援隊を率いて薩摩藩、長州藩にも影響力のある坂本龍馬と土佐藩船・夕顔丸で会談し、そこで坂本龍馬から示された船中八策の中の大政奉還論を土佐藩の藩論として採用。
そのために薩摩藩と薩土同盟を結んで、武力倒幕と平行して幕府や将軍・徳川慶喜に対して大政奉還の受け入れを働きかけます。
慶応3年10月14日(1867年11月9日)徳川慶喜は明治天皇に対して政権返上を奏上、徳川幕府は260年の歴史に幕を下ろしました。
幕末における尊王攘夷のまとめ
本来、日本の政治形態は武家政治が始まった鎌倉時代から、幕府が天皇から委託されて政治を行う大政委任論(たいせいいにんろん)が確立していました。
このため幕府に統治能力がないと判断されると、次の政権は常に天皇中心の国家体制が考えられ、これが尊王論となっていきます。
これに外敵を打ち払うすなわち攘夷を行うことが一つになった尊王攘夷論は、当時の若者たちにとっては自然な考え方だったのかもしれません。
幕末では尊王攘夷に熱中し、時代を動かそうとして多くの若者が命を散らしました。幕末とは、若者たちが一つのことをみんなで目指した、熱く燃えた時代だったのです。