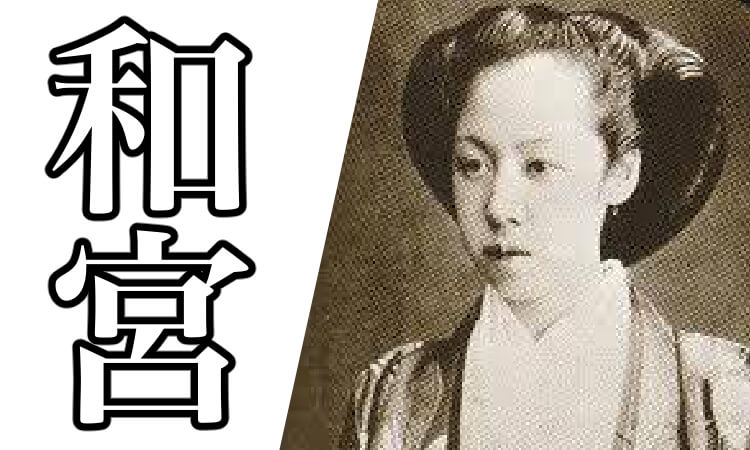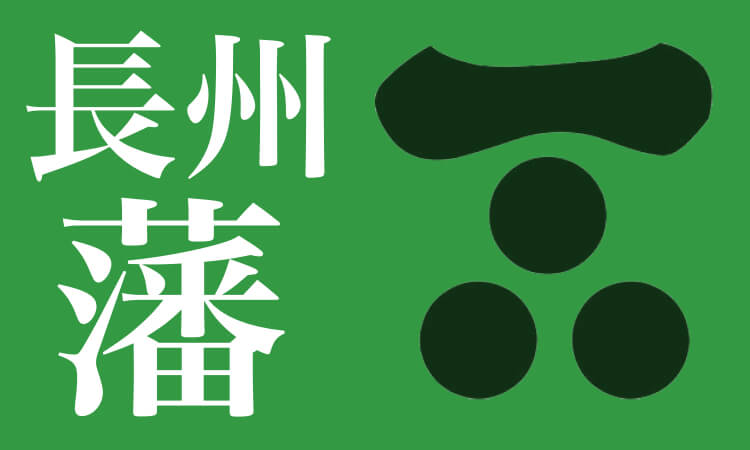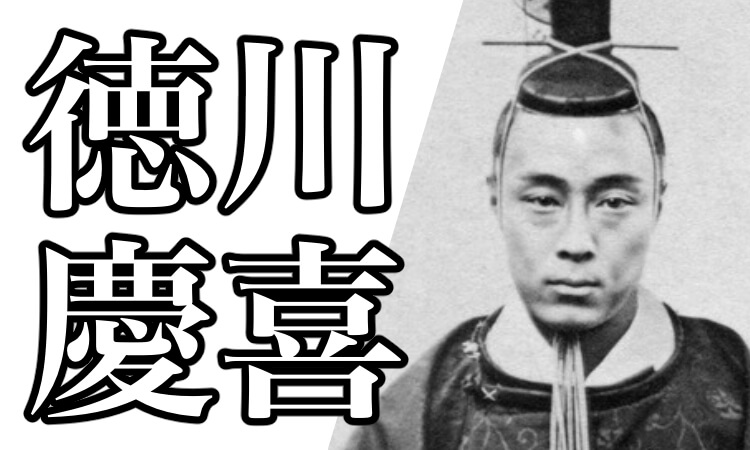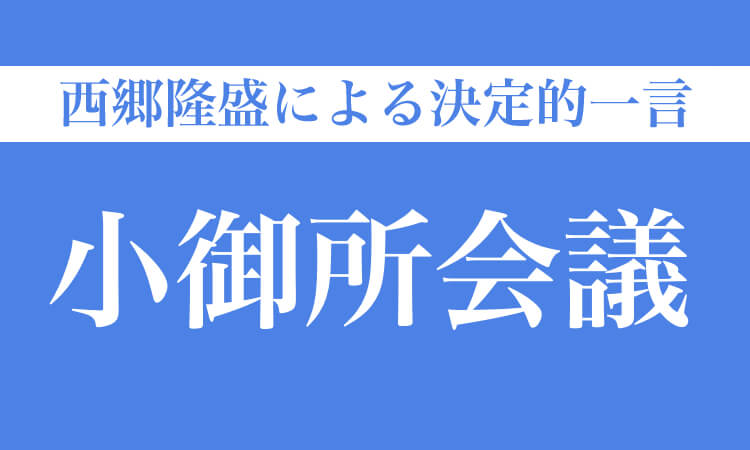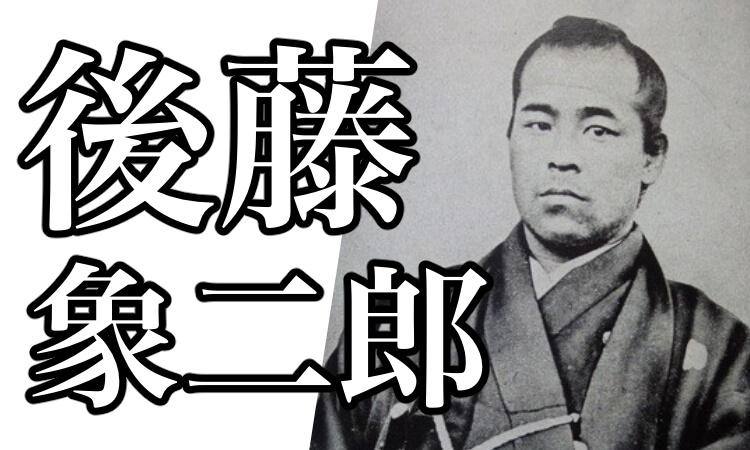ペリー率いる黒船の浦賀来航以来、爆発的な勢いを見せて日本中に広まった幕末の尊王攘夷論。
これらを支持したのは主に下級藩士や少壮の公卿、学者、一部の知識人で、この時代の政治に決定権を持つ藩主や上級武士、名門公卿などはこれらの動きを見て見ぬふりをするか、押さえつけるかで積極的に日本の行く末を論じるものは少なかったようです。
しかし、その中で一部の見識が高いと言われた越前藩主や薩摩藩主、維新の立役者の一人である西郷隆盛らは一時期、朝廷と幕府を融合させて幕藩体制を強化、回復させ、幕末の難局を乗り切ろうとする政策を推し進めようとしました。
これが公武合体論で、尊王攘夷論とは別軸として幕末の政治形態の考え方の一つになります。
今回はこの公武合体論がどこから生まれてきてどこへ進んでいったのか、その政策や運動、西郷隆盛との関係を含め、幕末の時間の流れに沿って解き明かしたいと思います。
公武合体論登場の背景
公武合体論が登場することになった背景には、急進的な尊王攘夷派と極端な佐幕主義との対立による国内政治の混乱を収集する必要性に迫られた事があげられます。
公武合体論を掲げる勢力は3つあり、それぞれに思惑がありました。
1つ目の勢力・徳川幕府
1つ目の勢力は徳川幕府で、日米修好通商条約の締結で朝廷との関係だけでなく、幕府内や諸藩との間にも亀裂が入り、その関係修復を急ぐ必要がありました。
2つ目の勢力・薩摩藩
2つ目の勢力は穏健的尊王攘夷派と言われる薩摩藩に代表される勢力です。
尊王攘夷のスタンスですが、急進的な改革は望まず緩やかに改革していく路線を望んでいました。
この勢力はのちに尊王開国、そして開国倒幕へと変化していきます。
3つ目の勢力・譜代大名など
3つ目の勢力は徳川の譜代大名や見識が高いと言われた大名に多く見られる勢力で、代表格は越前藩主・松平春嶽(まつだいらしゅんがく)です。
公議政体論と言われる大名による上院、公家や藩士、知識人による下院を創設し議会によって政治を行い、徳川家を元首格として扱うことを前提にした考え方を持つ勢力です。
この3つの勢力が協力して急進的尊王攘夷に対抗しようとしました。
公武合体論の進行と展開
公武合体の動きを最初に見せたのは徳川幕府でした。
日米修好通商条約の締結を無勅許で行ったため、朝廷との関係が危うくなり幕藩体制を支える雄藩と幕閣とが14代将軍継嗣問題で一橋派(15代徳川慶喜を推した)と南紀派(14代徳川家茂を推した)に分裂、徳川幕府は危機的状況を迎えます。
朝廷と幕府の関係を強固に
大老・井伊直弼(いいなおすけ)暗殺後、老中首座となった安藤信正(あんどうのぶまさ)は孝明天皇の妹・和宮と将軍・徳川家茂との結婚によって幕府の権威回復を狙い、朝廷側も将来の攘夷実行に向けて侍従・岩倉具視(いわくらともみ)らがこれに協力、無事降嫁となりますが安藤信正は坂下門外の変で負傷、失脚します。
安藤失脚後も幕府の公武合体政策は続いたため、雄藩の中に朝廷と幕府の間を取り持つ動きが出てきます。
島津久光が公武合体に貢献
薩摩藩の島津久光は自らが上京し、自藩の急進尊王攘夷派を粛清し(寺田屋事件)、朝廷から幕府に勅使を送らせ、公武合体派の一橋慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を政事総裁職に就けることに成功。
安政の大獄で処分を受けた山内容堂(やまうちようどう・前土佐藩主)らの処分も撤回させ、公武合体派の勢力を強化します。
公武合体派と尊王攘夷派の対立
公武合体派が体制を整え和宮降嫁が整った頃、京都には天誅の嵐が吹き荒れ、急進的尊王攘夷派が朝廷を牛耳り、その盟主は長州藩でした。
時の孝明天皇は極端な攘夷論者で、これに乗じた長州藩や尊王攘夷派志士は佐幕派や公武合体派を排除して朝廷を動かし、1863年1月将軍・徳川家茂(とくがわいえもち)に攘夷実行を確約させ、松平春嶽も政事総裁職を辞任。
他の公武合体派藩主も京都を離れ、京都での公武合体派は危機的な状況に追い込まれます。
急進派の長州藩を京都から追い出す
急進的尊王攘夷派の専横を食い止めるべく、薩摩藩は佐幕派の会津藩と手を組み、八月十八日の政変で長州藩、攘夷派公家や志士を京都から一掃し、朝廷政治を掌握すると朝命により参預会議(さんよかいぎ)を召集しました。
幕府からは老中、一橋慶喜、松平容保(まつだいらかたもり・京都守護職)、雄藩からは松平春嶽・山内容堂・伊達宗城(だてむねなり・前宇和島藩主)・島津久光らが集まり、国家の重要議題を話し合う会議が幕府成立以来はじめて雄藩諸侯の参加によって行われます。
公武合体派の衰退と倒幕への動き
公武合体派の悲願であった参預会議でしたが、一橋慶喜の露骨な島津久光排除や、重要議題の解決に結果のでない状況が続き、会議は空中分解し藩主たちは参預を辞任し京都を退去します。
一橋慶喜は将軍後見職を辞任すると新設の禁裏御守衛総督(きんりごしゅえいそうとく)に朝廷から任命され、二条城に足場を固め、京都守護職・松平容保、京都所司代・松平定敬(まつだいらさだあき)らと江戸幕府から距離をとって独自の活動を行います(一会桑政権・いちかいそうせいけん)。
薩長同盟の成立から倒幕へ
この後、15代将軍家となった徳川慶喜と対立した薩摩藩は倒幕へと進路変更した長州藩に接近し薩長同盟を締結。
島津久光は徳川慶喜に対抗するため再び山内豊信・伊達宗城・松平春嶽を呼び出し四侯会議(しこうかいぎ)を開きますが、徳川慶喜の政治力に対抗できずに会議は崩壊、薩摩藩はついに公武合体を諦め、幕府に対して武力討幕へと舵を切ります。
薩摩藩の脱落で公武合体派は解体状態となりますが、越前藩と土佐藩は内戦回避のために徳川慶喜を説得し、1867年、大政奉還を実現させ、一時的に武力討幕は回避されました。
公武合体と西郷隆盛
1868年に京都で明治天皇や総裁・有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)を始め、岩倉具視ら公家と山内容堂ら雄藩連合の藩主経験者の議定、参与として薩摩藩・西郷隆盛、大久保利通(おおくぼとしみち)、土佐藩・後藤象二郎(ごとうしょうじろう)らが参加して小御所会議が行われました。
最大の案件は将軍を辞した徳川慶喜の扱いとその領地の返還でした。
西郷隆盛の気迫の一言で会議が進展
徳川慶喜の排除を狙う岩倉具視や大久保利通と、慶喜を擁護する松平春嶽、山内容堂らが激しく対立、議定の多くが慶喜擁護に傾きかけたところで、一旦休憩になります。
この休憩中に薩摩藩士・岩下方平(いわしたみちひら )が会議の警備兵を指揮していた西郷隆盛を呼び出し会議の進行状況を説明すると、西郷は控え室の岩倉具視に対して「短刀一本あれば片が付く」と、岩倉に反対派と差し違える覚悟を迫り、この気迫に押された岩倉は短刀を忍ばせて会議に戻ったと言われています。
この逸話は広島藩主浅野長勲(あさのながこと)の口述記である「浅野長勲自叙伝」にのみ記載があり、「徳川慶喜公伝」「岩倉公実記」など同時期の史料にはないため事実かどうかは不明となっています。
公武合体派の消滅と戊辰戦争
結果的には西郷の一言が効いたのか、徳川慶喜が自主的に官位を辞し、領地の返納を行うことで決着します。
しかし、倒幕の意思表示を明確にした岩倉具視や薩摩藩と同じ公武合体派であった戦争回避を唱える越前、土佐とが対立する形となり、薩摩藩は仕方なく妥協していくことになります。
西郷隆盛のテロ行為が幕府との戦いへ
このため徳川慶喜擁護論が強まり、新政権へ徳川慶喜が参加することまで話が及ぶことになり、西郷隆盛はこれを押し返すため長州藩の赦免とともに長州藩兵が入京してきたことをきっかけに、江戸で薩摩藩の息の掛かった者たちに放火や略奪、暴動などの不法、挑発行為を起こさせて幕府側を刺激します。
これに乗せられた幕府側は江戸薩摩藩邸を焼き討ちする暴挙に出て、これに呼応した大阪の幕府軍は京都へ進発、これと薩摩藩兵が鳥羽街道で衝突し、鳥羽伏見の戦いへ発展します。
西郷隆盛の策に乗せられた幕府はこの後、敗戦と撤退を繰り返し、戊辰戦争も惨敗しすべてを失うことになります。
明治新政府の中での公武合体論の行く末
小御所会議は議会の開催と言う点では画期的な出来事でしたが、議会の運営や参加者の資格と言う点で多くの問題点も残しました。
このため新政府の会議では三職(総裁、議定、参与)の下に、徴士(ちょうし)と言われる諸藩で有能な藩士を議事官として採用し円滑な議会運営を行い、彼らが後の官僚として政府を運営していきます。
自由民権運動に繋がる
公武合体論は衰退しますが、内戦回避の考えや議会の開催と言う考え方は、大政奉還論を推したり、船中八策を考えた坂本龍馬(さかもとりょうま)の影響を受けた土佐藩出身者に受け継がれ、後藤象二郎や板垣退助(いたがきたいすけ)らの自由民権運動に繋がり、海援隊士だった後の外務大臣・陸奥宗光(むつむねみつ)や思想家の中江兆民(なかえちょうみん)もこれに賛同しました。
自由民権運動は憲法の制定や議会の開設、普通選挙の実施、政党政治の確立、言論の自由や集会の自由など多くの政治的改革を掲げて盛り上がり、1890年11月29日、第一回帝国議会が開かれるまで続きました。
幕末に誕生した尊王攘夷と公武合体と言う考え方は時代の流れの中で変節し、尊王攘夷は明治新政府の誕生の原動力となり、公武合体は憲法制定、帝国議会開設に繋がります。
対立し、多くの血を流した2つの考えは奇しくも明治新政府の誕生と発展には欠かせなかった理論だったのです。